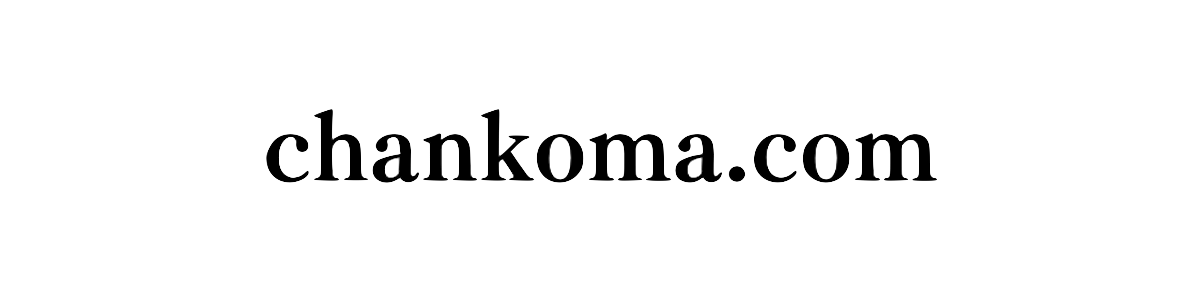「集中力が続かない」
そう思う人は結構多いと思います。
本を読もうとしていたけど、ゲームをしてしまった。
筋トレしようとしていたけど、スマホを触ってしまった。
集中力が継続しない人は結構多いと思いますが、集中力を続ける方法として効果的なのが「タスクシフト」することです。
集中力を高めるためには

まず先延ばしにするのが僕は嫌いなので、集中力を高める方法から伝えておくと、「30分ごとにタスクをシフトする」ということをやって見てください。
というのも、そもそも人間というのは、集中力があると見せかけて、あまりありません。
ある大学の研究では「人間の集中力は30分持てばいい方だ」ということさえ言われています。
冒頭で伝えた「本を読もうとしてたけど」だとか「筋トレをしようとしたけど」といった「集中力の欠落」というのは、人間であれば致し方のないことなんですね。
つまり集中し続けるというのは、どれだけトレーニングを積んだとしても難しいということ。
それは好きなことであっても、楽しいことであっても、同様です。
好きなことであっても、同じことを何時間と繰り返していては集中力は低下し、飽きてきてしまう。
その飽きてきたタイミングというのは、同時に「別のことに集中が向いている」ということを意味するので、集中力が継続する30分をめどに「タスクをシフト」していくことで、集中力が継続していくということが言えるわけです。
根拠

その根拠はどこにあるのか。
ということですが、これはトロント大学が出した論文で明らかになっていて。
トロント大学が17621人を対象に、試験対策などを載せたウェブトレーニングをしてもらうように促しました。
そして17週間もの間、この1万7千人を超える被験者の行動をチェックして、「ウェブトレーニングでのアクセス」を観測しました。
この実験がどういう意味を表しているのかというと、1万7千人を超える被験者たちが、途中でウェブトレーニングへアクセスしなくなれば、「興味や好奇心の低下」が見られるため「集中力」が散漫になっていることがわかります。
一方でアクセスが変わらなければ、「興味や関心の低下は見られず」、「試験対策」に対しての集中が継続されていることがわかります。
そうして、17週間もの間、1万7千人の被験者を追って行ったわけですが、この実験の結果「最初のアクセスと最後のアクセス」では、アクセス数への変化は見られなかったそうです。
つまり、「最初から集中して取り組んでいた人は最後まで取り組めた」ということが明らかになり、「集中力を継続させることはできる」ということが証明されたわけです。
このことからわかるのは「集中力」というのは、継続させることができるということ。
そして、その集中力を持続させるために大切になってくるのは、「飽きさせない工夫」だということです。
人というのは、冒頭でも伝えた通り、いくら好きなことであったとしても、それを永遠繰り返していては、絶対に飽きてしまいます。
そうして好奇心が失われて行った途端に「集中力」が欠如し始め、飽きが訪れて行ってしまいます。
ただ、トロント大学の研究にあったように、集中力が低下したといことは、「集中力」がなくなったのではなく「別のところに集中力が移動した」という解釈の方が正しいわけです。
ですから、別のところに移動した集中力を生かしてあげることが、「継続して集中力を維持」する方法だと言えるわけです。
応用方法

じゃあ実際に、どうやってこの集中力を高める方法を応用していけばいいのか。
僕の場合は、30分ごとにタスクシフトをしています。
例えば、僕の場合本を読むことが大好きです。
ただ、本を読むのが好きだからと行って、1日10時間も読めないし、多分1時間ぐらいしたら本を読む集中力はなくなり始め、スマホなどに注意がいってしまう。
しかし、これは先ほども伝えた通り、「集中力がなくなった」のではなく「集中力が別のところに移動した」という解釈です。
ですから、「30分間は読書をする」という形で、制限を設ける。
そして、その30分間は読書をするということに集中します。
その読書が終われば、次はこうして「ブログを書く」というタスクにシフトします。
ちょうど「本を読む」というタスクには飽きが来始めている頃なので、別のタスクをやるということですね。
その後も同様ですね。
「本を読む」
↓
「ブログを書く」
↓
「筋トレをする」
↓
「本を読む」
↓
こうすることによって、集中力を高い状態で維持し続けることにつながっていくわけです。
実際に僕もこのように30分間で、タスクをシフトするようにしてから、集中力が散漫になることを防げるようになったと実感しています。
また「アメトーク」であった、勉強大好き芸人のオリラジのあっちゃんも、これと似たような話を言っていますね。
オリラジあっちゃん曰く。
「数学を勉強して、飽きたら英語。英語を勉強して、飽きたら社会。こうして学習する項目を変えれば、飽きることはなくなる。
大好きなハンバーグでも毎食食べれば飽きる。この飽きた段階で多くの人が「休憩」をしようとするんだけど、結局休憩しても味は変わらない。
そうじゃなくて必要なのは「味変え」である。
味を変えることで、同じ勉強というカテゴリーでも使う脳は全く異なった部分を使うため、継続して勉強することができる。
だから、数学を勉強して、飽きたら英語。英語を勉強して飽きたら社会。というようにジャンルを変えていくのが有効だ」
そんな風に言っていました。
一見すると、長時間1つのことを続ける人が勉強ができるイメージがあったりしますが、ほとんどの人はそんなことできません。
長時間1つのことを続けられる人も、飽きはきますし、飽きがくれば集中力は低下します。
そのために、オリラジあっちゃんの言葉で言うなら「味変え」が必要で、その味変えをすることによって高い集中力を継続できると言うこと。
これは僕自身も取り入れて30分ごとにタスクをシフトするようなライフスタイルに変えましたが、結構効果的です。
僕は集中力が高くない方ですが、少ない時間だけ集中すればいいので、インターバルが多いマラソンを走っているような感覚で楽です。
実際にやってみた結果

んで。
このトロント大学の研究を知って結構な時間が経ちました。
実際にトロント大学の研究を知る前からも知った直後からも、「30分でタスクシフトをする」ということはやっていたんですよね。
そしてそれからもずっと続けていました。
なので、「継続してタスクシフトをし続けるとどうなるのか?」っていう体験談を伝えていこうと思います。
30分でタスクシフトするのはやっぱりいい
まずさきに結論から伝えると、やっぱりいいです。
30分でタスクをシフトしていくのは。
というのも、どんだけ楽しい趣味であっても、どんだけ楽しい仕事であっても、続けるのはしんどい。
僕自身も、「これは楽だな」って感じのタスクやノルマみたいなのであっても、やっぱり続けるのはしんどいです。
(ノルマがないから、自分にあえてノルマを課している)
で、実際に「30分で切り替えよう」ってなると、新しい刺激が入ってくるので、全然集中力が変わるんですよね。
体感として作業効率が1.5~2倍ぐらいには上がっているのかな、っていう体感があります。
具体的なシフトとしては、「ブログを書く」っていう作業を30分やったら、次は「読書」をする。
その次は、「散歩」に行く、というようにタスクをシフトしていっています。
こんな感じでやっていると、「飽き」を感じ始めると同時に別のタスクに移行するので、結構いいんですよね。
飽きは脳からのシグナル
で。
振り返ると、このトロント大学の研究を知る前って「我慢して続ける」みたいなのが美徳のように思っていたんですよね。
特に小学校とか中学校の時は、そうやって思う傾向が強かったように思います。
数学の勉強をしていて、解けない問題があって。
もう飽きてきているのに、ずっと達成できるまで数学を続ける、みたいな。
でもね。
飽きって脳からのシグナルで、「次のことをやりたい」っていう信号なんですよね。
で。
これも後に知ったことですが、実は「解決できない問題」に対しても、別のことをやったり、あえて時間を置くことによって、より良いアイデアが出ることが分かっています。
なので、「飽きたり躓いて進まないにもかかわらず、根性で続ける」って、生産性をガクッと落とす行為なんですよね。
でも僕は、「諦めたらダメな人間だ」っていう風に思ってしまっていたんですよね。
そうじゃなく。
「飽きっていうのは、脳から次のことにシフトしていってほしい」っていうシグナルだととらえると、本当にいいタイミングでシフトできます。
なので、「飽きた」という感情って決して悪いものじゃないんですよね。
それを知ることがすごく大事だなぁっていうのは、やってみて痛感しました。
飽きているのに30分以上続けてみた結果
でね。
「飽きた」という感情は決して悪いものじゃなく、脳から次のタスクへシフトしていってほしいというシグナルだ、という風に感じられたのはある経験があったからで。
ある分野で、飽きているにもかかわらず、1時間も2時間も続けてみたんですよね。
その結果、その分野でどれぐらい生産性のあることができたのかっていうと、まったく進まなかったんですよね、僕の場合。
むしろ30分で区切ったときと全くおんなじぐらいしか進まなかったんですね。
分かりやすくこのブログで考えてみたら、僕の場合、「3000文字」ぐらいの記事だったら、インプットも含め大体30分ぐらいで終わります。
3000文字で1記事完成だとすると、単純計算、2時間ブログ執筆に費やしたら、4記事分書けるはず。
でもそうは単純じゃなくって。
ガッと集中するから、30分で書き終えられるわけで、そこから飽き始めているのにも関わらず、続けた場合、たぶんですけど2時間終わったとき、合計で2~3記事ぐらいが限度だと思います。
飽き始めたら、そこから集中力がグッと落ちて、その分生産性も下がるので、かなり作業効率としては悪いんですね。
だから、30分なら30分と区切って、ガッと集中して短時間で終わらせて、作業をシフトする。
これがトータル的に見て作業効率的にも、生産性においても、重要なことなんだなって痛感しましたね。
まとめ
つまりまとめると、集中力が低いと言うことで悲観する必要は全くなく。
集中力というのは、どれだけトレーニングしている人でも「30分間」集中するのがやっと。
ということは、集中力を高い状態で維持し続けるためには「タスクをシフトする」ということが効果的で、タスクシフトをしていくことで高い集中状態を維持することができるということ。
そしてタスクシフトをしていく際には、「なるべく同じ頭を使わない」方がいいですね。
資格勉強などの「暗記もの」があるのであれば、次は「アウトプット」などの練習問題に時間を割いたり。
読書をしたのなら、次は「運動」などのタスクにしたり。
なるべく同じ脳の場所を使わないようにタスクをシフトしていくのがポイントかと思います。