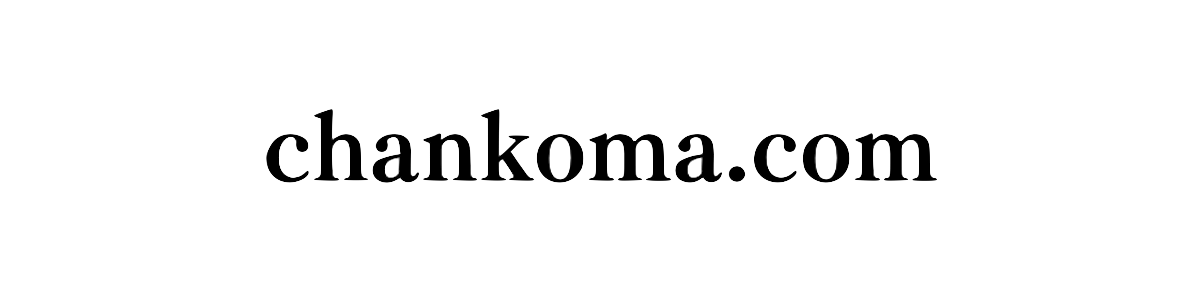今回はタイトルにある通り。
「同僚や上司と仲良くなる方法」に関して、面白いことを知ったので、それをシェアしておこうと思います。
多くの人が「仲良くなるためには共通点を見つけること」という風に言っていますが、確かに共通点を見つけることは人と人とが仲良くなるために強力なツールになり得ます。
その中で「特に見つけると仲良くなりやすくなる」共通点を先に結論として伝えておくと、
- 人生における態度や思想
- コミュニケーションスタイル
この2つにおいて共通点を相手と見つけることが出来れば、急速に相手との距離を縮められることが分かっています。
今回はそんな人間関係に関する面白い話をしていこうと思います。
職場に友人を3人以上作ると、幸福度が2倍になる
そもそもの話。
職場や仕事における「人間関係の重要性」の話からしていくと、より今回の「人と仲良くなる方法」を知る意味があると思うので、解説していくと。

以前このブログの中で取り上げた「最高の職場環境」という記事の中で、「職場に友人が3人以上いると、人生における満足度が約96%も上昇する」という研究結果を、アメリカの調査会社が結論付けています。
また給料に対する満足度も、現状の年収の3倍と同等の満足度という試算も出していて、「職場環境」や「職場における人間関係」が人生においてかなり重要なポイントになることはすでに知られている事実です。
これは逆もしかりで。

上記記事におけるハーバード大学の研究なんかを見てみると「隣に仕事ができない人がいると、生産性が10%低下する」という研究なんかも出ています。
つまり、良い人間関係が気づければ、生産性はもちろん給料に対する満足度や人生における充実度が高まり、悪い人間関係などが会社内ではびこると、自分自身にも大きな悪影響がもたらされる、ということなんですね。
だからこそ「仲いい人を作る」ということは、自分が想像する以上に大切なことで、今回紹介する「人と仲良くなる方法」を知っておくと、様々なシーンにおいて役に立ってくるわけです。
どうすれば人と仲良くなれるのか。

では一体どうすれば人と仲良くなれるのか?という部分ですが、これは多くの方法があるかと思います。
ただ、タイトルにもある通り急速に相手との距離感を縮めるために効率的なのか「共通点を見つけること」が、有効的だということが分かっています。
なぜこの共通点を見つけると仲良くなりやすくなるのかというと、「類似性と帰属意識」が関係しているとされています。
類似性と帰属意識とは
類似性というのは、簡単に言えば「似ている」ということがポイントとして挙げられます。
僕ら人間というのは会社や家族、学校というコミュニティを形成してい生きています。
学校でもそうだし、会社でもそうですが、「似ている人」っていうのは、塊を作り、コミュニティを形成します。
「似た者同士」という言葉がありますが、これはコミュニティ形成し生き残ることがDNAに刻まれており、そのコミュニティを形成するための条件として「自分と似ていること」が挙げられるわけです。
それが類似性。
そして帰属意識というのは、その「コミュニティに居たい」という想いのことで、類似性を持って集まったコミュニティが心地よい場合、帰属意識が働くので「この人と一緒にいたい」という感情が芽生えるわけです。
つまり何が言いたいのかというと「共通点を見つけると仲良くなれる理由」というのを深く考えていくと、「類似性を感じることで仲良くなり、コミュニティが形成され、帰属意識の働きで、この人と一緒にいたいという感情が生まれる」
だからこそ、「共通点を見つけると仲良くなれる」ということが言えるわけですね。
相手と一瞬で仲良くなれる「黄金の共通点」とは

とまあここまでが前段階で、ここからが本題です。
ただ単に「共通点を見つける」といっても、探せば多くの共通点が見つかります。
「男同士」であれば「男である」ということが共通点になりえるし、「同じ会社で働いている」ということであれば、「同じ会社員という立場」だって共通手になりえる。
つまりここでわかることというのは「共通点といっても、仲良くなれる強さの割合」が共通項によって異なる、ということなんですね。
男同士だから仲良くなれるとは限らないし、逆に「見知らぬ外国の土地で日本人に出会う」ということがあれば、急速に仲良くなれるでしょう。
いわば「仲良くなりやすい共通点」というものが存在するわけです。
それを調べてくれたのが、アメリカのイリノイ大学が2013年に行った研究でした。
この論文では「類似性と帰属意識」に関することを研究し、被験者200組のカップルを集め、「どんな共通点を持つ人が仲良くなりやすいか?」ということを調べていったのでした。
この研究では主に「6つの種類の共通点」があることをベースにして調べていきます。
共通点の6種類
その6つというのが、
- 生活の背景
- 人生における態度や思想
- 趣味や休日の過ごし方
- コミュニケーションスタイル
- パーソナリティ
- 外見
この6つでした。
簡単に一つ一つ見ていくと、
- 生活の背景
これは要するに「出身地」や「地元」といったことで、「同じ大学」という共通点を見つけるケースもあるし、「地元が一緒」ということで仲良くなった人も多いかと思います。
- 人生における態度や思想
次にこれは「どういった価値観で人生を生きているのか」というポイントで、少し抽象的ですが「生きる上での信念」などに近いものです。
- 趣味や休日の過ごし方
次はこれですが、いわゆる「共通点を見つける」ということで、一番ポピュラーなのがこの休日の過ごし方や趣味を聞く、ということじゃないかなと思います。
- コミュニケーションスタイル
次いでコミュニケーションスタイルというのは、「聞き役が多いのか」はたまた「話す方が好きなのか」「論理的に話すのか」「感情的に話すのか」といったコミュニケーションのスタイルというのが項目として挙げられています。
- パーソナリティ
次いでパーソナリティですが、これは「人見知りしがち」だとか「内向的、外交的」といった性格などを表している項目です。
- 外見
そして最後が外見。これはシンプルに服装やファッション、など外から見える情報で共通点を見出していく、ということになります。
一番仲良くなれたのはこれだ
- 生活の背景
- 人生における態度や思想
- 趣味や休日の過ごし方
- コミュニケーションスタイル
- パーソナリティ
- 外見
アメリカのイリノイ大学では、これら6つの共通点のうち「どれが一番仲良くなるために重要な共通点(類似性と帰属意識を産むのか)なのか」
ということを調べていったわけですが、冒頭にも伝えた通り答えは
- 人生における態度や思想
- コミュニケーションスタイル
この2つであることが分かりました。
つまり相手と仲良くなるためには「人生のおいて何を大事にしているか」といった信念や思想と、「どういったコミュニケーションスタイルをする人なのか」という共通点を探すことが一番重要だということが、この研究により判明したのでした。
逆に、効果が薄かったのは
- 外見
ということも同時に分かっていて、ファッションや容姿などの共通点を見つけても、心の底から仲いいと思えるような関係にはなりづらいことが分かりました。
次いで効果がないわけではないですが、さほど重要でもないのが、
- 趣味や休日の過ごし方
という項目がランクしていて、多くの人が「共通点を見つける」ときに一番聞きそうな趣味などは、さほど仲良くなるうえでは重要じゃない、ということも見えてきています。
それ以上に3番目にランクインしていた
- パーソナリティ
という項目も、仲良くなるうえでは重要なポイントとして挙げられていて、人生における態度や思想やコミュニケーションスタイルよりは劣るものの、重要なポイントであることが分かっています。
ここまでの感想とまとめ

ここまでを見ていくと、共通点を見つけ仲良くなるということに関して、よく使われる「趣味や外見」といったことは、実はあまり効果が期待出来ず、「うわべだけの存在」としての関係になりがちな共通点だということが分かります。
これは確かにと思える内容で、「身長が同じ」だとか「同じブランドが好きだ」だとか、そういった外見や趣味というものが似ている人は、「友達」に多い気がしています。
ただ、「親友」と呼べる間柄の人は外見がまったく違っていたり、趣味も違っている人が個人的には多い気がしました。
その一方で「同じ価値観」であったり、「人生における目標が同じ」であったりと、もっともっと「深いところでつながっている」ことが友達と親友とを分けるポイントなのかなって感じました。
そして友達と親友とを分ける明確な違い、というのを言語化すると
- 人生における態度や思想
- コミュニケーションスタイル
この2つに集約されるのかな(特に人生における態度や思想)、というのが僕の感想でした。
本当に仲良くなるために見つけたい共通点をまとめると、
- 人生における態度や思想
- コミュニケーションスタイル
- パーソナリティ
この3つを見つけると、本当に親友と呼べるぐらいの人と出会えるかもしれません。
応用方法

ここまでがイリノイ大学の研究を見て、仲良くなるために重要な「共通のこと」として、伝えたいことでした。
ここからさらに、「具体的に仲良くなる方法」をイリノイ大学の研究から、さらに深堀して実践していく部分にまでフォーカスして分析していこうと思うんですね。
僕的にポイントになると思っているのは、先ほど挙げた、
- 外見
- 趣味や休日の過ごし方
- 生活の背景
この部分です。
基本的に「外見や趣味」などの共通点は、「うわべだけの付き合い」になってしまうことがあると先ほどは伝えましたが、「アイスブレイク」に使えることは間違いない。
アイスブレイクというのは、「初対面で心を閉ざした人に対して、心を許していく状態にする」ことをアイスブレイクというわけですが、これが「外見や趣味」で僕は効果があると思うんですね。
というのも、まったくの初対面や面識のない相手に対して、最初からパーソナルなことは聞けないですし、人生における態度や思想を聞くのもいきなりすぎて、引かれてしまう可能性さえある。
裏を返すと、人生における態度や思想といった深い話っていうのは、「かなり仲良くなった段階」でするのが基本なため、その「仲良くなり初め」には使えないということだと思うんですね。
だから、まずはアイスブレイクするために、「外見や趣味や休日の過ごし方」といったフランクな部分から共通点を探り、帰属意識を高めていく。
そのうえで、次に重要になるのは「パーソナリティ」かなと思っていて。
要するに、この段階で「自分と相手が波長が合うか?=もっと仲良くなりたいと思えるかどうか?」という基準が入ってくるんだと思います。
当然、性格が合わなければこれ以上仲を深めても意味はないし、お互いにとって苦痛でしょう。
「合うか合わないか」っていうのは、パーソナリティによって判断すべきなのかなっていう風には思います。
(嫌いだけど仲良くならなくてはいけない相手に対しては、そこまで重要視するべきポイントじゃないかとは思いますが)
この段階である程度共通点ができて、仲良くなり始めているなって感じたときに、より深い仲になっていくために、
- 人生における態度や思想
- コミュニケーションスタイル
この2つの共通点を見出していくのが、より実践的にわかりやすいステップなのかなって思いますね。
要するに、僕としては「趣味や外見」というのは効果は薄いが、効果が薄いがゆえに「使いどころはある」と思っていて、仲良くなり初めの段階で「人生における思想や態度」っていうレベルの深い話ってできないと思うんですね。
とすると、せっかくためになるこの論文を生かしきれない。
なら、アイスブレイクの段階であれば十分効果はあるし、仲良くなるきっかけにはできると思うんですね。
なので、僕としての応用方法を伝えるのであれば、
- 外見
- 趣味や休日の過ごし方
- 生活の背景
- パーソナリティ
- コミュニケーションスタイル
- 人生における態度や思想
こうした順番で、活用していくのがいいんじゃないかなって思います。
実際にこれらは効果の差はあれど、いづれも効果が確認されているものなので、無駄なく活用するべきで、段階によって使い分けることが重要なのかなって思いましたね。
ぜひ参考にどうぞ。