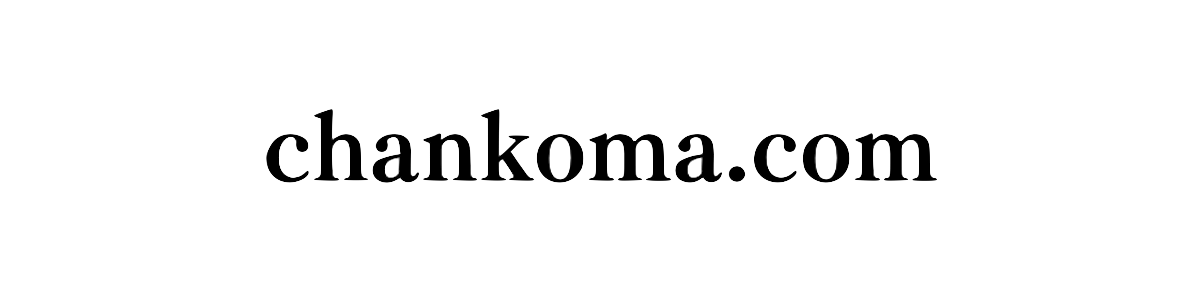今回はタイトルにある通り。
「習慣」に関して面白いことを知ったので、それをシェアしておこうと思います。
良く習慣にしたい事柄として「運動」が挙げられ、「ダイエットしたいからジムに通いたい」という風に考える人が多くいます。
この「ジムに通う」といった運動って、習慣化の中で結構難しい分類なので、よく研究の対象として挙げられるんですよね。
さらに言えば、「ジムに通いたい」という習慣を身に着けるとき、おおよそ「仲間を作って一緒にやる」という方法が提唱されたり。
はたまた「報酬やご褒美を設定する」というやり方があったり、「ライバルを作る」という方法などが存在しています。
今回紹介するのは
- 仲間を作る
- 褒美を与える
- ライバルを作り競争させる
この3つのうちどれが一番「ジムに通いを継続できたのか?」といったことを検証してくれた実験があるので、紹介していきます。
今回もいつも通り結論から伝えておくと、「仲間を作る」としたグループが、一番ジムに通う割合が高くなったので、もし仮にジムに通うことや運動などを習慣にしたい人がいた場合は「仲間を作り一緒にやる」ことを検討してみるといいかもしれません。
根拠
ではさっそく実験モデルと「仲間を作ることが一番習慣化しやすい」という根拠から解説していくと。
これはウエストチェスター大学が発表した論文が元になっていて。
ウエストチェスター大学が行った研究では181人を対象にして実験が行われました。
冒頭でも伝えた通り運動がまったく習慣となっていない181人の被験者を、3つのグループに分けていきます。
- 仲間を作る
- 競争させる
- 報酬を与える
この3つのグループに分けて、ジムに通い運動をしてもらう、ということをお願いしました。
具体的には「仲間を作る」としたグループは、参加者同士でペアになってもらい、一緒にジムに行ってもらうように促しました。
「競争させる」としたグループは、参加者同士がどれぐらい運動をしているのかを報告し、競争心に訴えていきました。
「報酬を与える」としたグループは、1回30分、週に3回以上ジムに通い運動をした場合に、お金を与えるという風に褒美を設定しました。
それぞれ3つのグループに分かれてもらい、3週間後に「どれぐらいジムに通い運動を行えたのか」といったことをウエストチェスター大学は検証していきました。
その結果わかったのは、
- 仲間を作る
- 競争させる
- 報酬を与える
上記の順番で、ジムに通う頻度が高く、「仲間を作る」としたグループが最も習慣化を行えていたことが判明しました。
具体的には、一番の最下位である「報酬を与える」としたグループでは「およそ2倍」の効果が確認されていて。
ジムに通う頻度は「週に1回未満」だった被験者が、平均して「週に1.5回」ほど通うようになり、最下位といっても2倍ほどの効果が確認されています。
次に2位だった「競争させる」としたグループは、およそ2.5倍ほど確認されていて。
ジムに通う頻度が週に2回以上という結果となりました。
そして1位だった「仲間を作る」としたグループは、ジムに通う頻度が週3回以上となり、効果は「3倍」ほどだったことが分かっています。
さらに言えば冒頭でも伝えた通り、「ジムに通う」ということを対象にして行っていますが、「体を動かす運動系」のことは習慣化としてかなり難しいジャンルになることが分かっています。
この「体を動かす運動系」において、約3倍の効果があったことから、他のジャンルであればもっと高くなることが想像できます。
つまり、何かしらを習慣化させたい場合は、「仲間を作り一緒にやる」ことを行うことで、習慣として定着し約成る可能性が高くなる、ということが言えるわけですね。
応用方法
では次に。
このウエストチェスター大学の研究をどうやって日常生活に応用していけばいいのか。
「友達がいない人はどうすればいいのか」
そうやって考える人も多いと思います。
一番効果が高いのはもちろん「仲間を作る」ということですが、同じ目標を持った仲間がそう簡単に集まるわけじゃないし、この「仲間をつくる」ということをハードルが高いと感じる人も多いかと思います。
ただ。
この研究の一番面白いポイントは「仲間、競争、報酬のいづれにおいてもある程度の効果が確認されている」というところなんですね。
効果の違いはあれど、
- 仲間=3倍
- 競争=2.5倍
- お金=2倍
いづれの効果が確認されているわけです。
なのでもし仮に「友達がいない」とした場合でも、競争やお金といったアプローチをかけることで、習慣化しやすくなることが想像できるわけです。

実際に上記のペンシルベニア大学の研究では、ある条件下での「ご褒美」には一定の効果があることが分かっています。
なので、友達がいないという場合は、「ペアを作る」ということよりは効果が劣りますが、2倍ほどの効果が確認されているので「報酬や褒美」を設定するのも1つの手です。

実際にどういったご褒美の設定がいいのか?やよりご褒美の効果を高める方法に関しては上記記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
続いて「競争」ということに関してですが、これも一見すると「仲間」がいないと競争ができないように思えます。
もちろん「一緒にやっている参加者の進捗状況」などが「競争心」に火をつけることが多いので、広い意味でとらえれば「仲間」が必要かもしれません。
ただこれも応用次第で。

上記記事で解説しているハーバード大学の研究では「隣の人が仕事ができない人だと自分自身の生産性も低下する」ということを報告しています。
このことを逆に応用すると、「ジムで頑張っている人の隣でトレーニングをする」ことによって反対の正のエネルギーを獲得することが出来るようになります。
つまり、見ず知らずの人だが、同じジムに通う人と「競争」することが出来、その人からエネルギーをもらうことが出来る、ということですね。
ジムの広いスペースで「どこでトレーニングするか?」といった工夫でも「競争」ということは応用が出来そうです。
そして最後の「仲間を作る」ということですが、これは「物理的な仲間」ではなくてもある程度の効果が得られるわけです。
となると、「SNS」などで運動やトレーニングを頑張っているコミュニティに参加し「オフライン」での友達と一緒にやることで、その恩恵を受けることが出来るようになります。
内気な人であれば、発信はせずに「人が運動やトレーニングなどを頑張っている発信を見る」ということでも共同感覚をはぐくむことが出来ると思うので、疑似的な仲間を作ることだってできます。
とは言え、一番は「物理的な仲間」であることは変わりないと思いますので、一緒に頑張ってくれる友達を見つけるのが一番ですが、もし仮に見つからない場合はSNSなどを通して、同じ志を持った人を見つけるのも一つの手かもしれません。
まとめ
少し長くなったので、最後にまとめておくと。
「仲間or競争or報酬」のうち、一番ジムに通えた割合が高かったのは「仲間」。
効果の違いは
- 仲間=約3倍
- 競争=約2.5倍
- 報酬=約2倍
いづれの順位と効果の違いがウエストチェスター大学の研究によって証明された。
つまり、何かしらの事柄を習慣にしたい場合は仲間を見つけて一緒に行うと実行しやすい。
ただ、友達がいなかったりする場合は、他の「競争、報酬」といったやり方も効果がないわけではないため、環境や自分に合うかどうかで変更してもよい。
また、SNSなどを活用したりして、仲間や競争相手を見つけることもできるので、いくらでも応用が可能。
まとめるとこんな感じですね。
ぜひ参考にどうぞ。