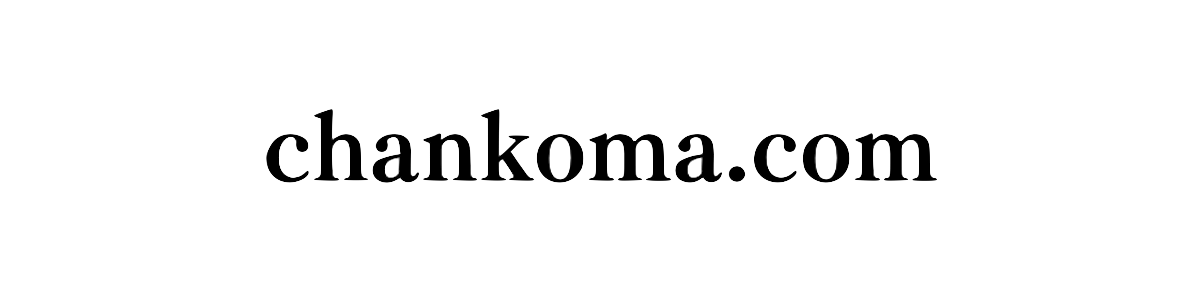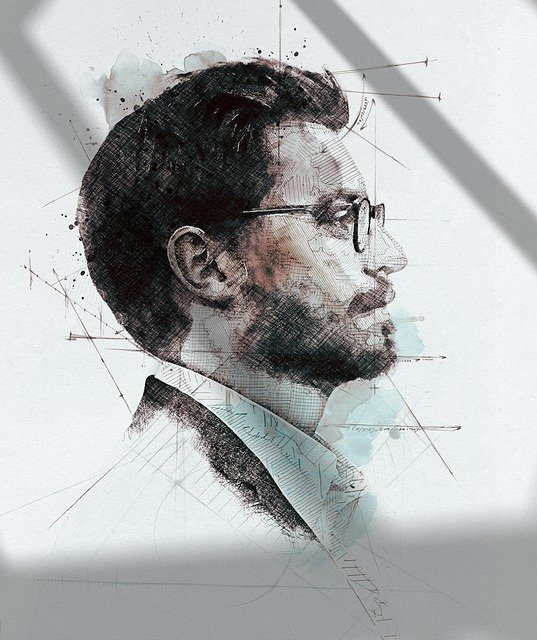今回はタイトルにある通り。
「悪い習慣をやめる方法」に関して、面白いことを知ったので、それをシェアしておこうと思います。
その方法っていうのが、「代替えイフゼンルール」というもの。
良い習慣を作る上で欠かせないこと

この代替えイフゼンルールに関して説明する前に、「良い習慣の作り方」を知る必要があって。
そもそも良い習慣を作るために、科学的に効果が証明されているものの1つで「イフゼンルール」というものが存在します。
「新しいことを習慣化するのに超絶オススメの簡単テクニック!」
のイフゼンルールに関して、詳しいことは上記記事で解説していますが、カンタンに説明すると。
「〇〇の時、〇〇をする」
このように条件を決めておいて、行動に移すルールのことを、イフゼンルールと呼びます。
その名の通りで「朝起きたら、歯を磨く」というように、ifにある条件をもとに、thenの行動をする。
これがイフゼンルールなわけですが、このイフゼンルールというのは、通常の決め事よりも「脳への訴求力」が強いため、「やらなくちゃ!」という感情に強く訴えてくれるため、より習慣化に向けての行動を促す結果につながるとされています。
コロンビア大学のハイディ教授なんかの本を見ていくと、習慣化には「このイフゼンルールだけでいい」とするぐらい、心理学的に重要だとされているテクニックです。
悪い習慣を断ち切る代替えイフゼンルールの根拠

まずこのイフゼンルールに関して理解してもらった上で、「代替えイフゼンルール」っていうものとその効果に関して解説していくと。
代替えイフゼンルールっていうのは、例えば「健康に気を使っているのに、飲み過ぎてしまう」という状態があったとします。
このような状態の時、多くの人は「アルコールを飲まない」と決めてしまいます。
ただ、「カリフォルニア大学式!悪い習慣を約3倍も辞められる科学メソッドを紹介!」
この記事でも伝えている通り、悪い習慣ほど訴求力が強いため、なかなか誘惑に打ち勝てないのが人間です。
その際に、「アルコールを飲まない」と決めるのではなく、「お酒を飲みたくなったら、水を飲む」というように、代替え案を考え、ルール化をするのを代替えイフゼンルールという風に言います。
このイフゼンルールに関して、どういった効果があるのか、というのを研究したのが、オランダのユトレヒト大学で。
このユトレヒト大学では、3つのイフゼンルールに関して、研究を行いました。
その上で、どういったイフゼンルールが一番効果的で、どういったイフゼンルールが効果がないのかを検証していきました。
要するに、「悪い習慣」を断ち切るために効果がないのは、どういった要素があるのか。
こういったことを調べて行ったわけです。
調べて行った3つのイフゼンルールというのが、
- 代替えイフゼンルール
- 無視イフゼンルール
- 否定的イフゼンルール
この3つでした。
代替えイフゼンルールは、先ほど説明したので割愛しますが、無視イフゼンルールというのは、「お酒が飲みたくなっても無視をする」というもの。
そして、「否定的イフゼンルール」というのは、先ほどの例えのように「お酒が飲みたくなったも、飲まないようにする」というように、「〇〇しない」というように決めた決めたごとのことを指します。
イフゼンルールを使っていない、と思っている方でも、往々にしてこのルールは使っていて。
大半の人は「お酒をやめたくてもやめられない」とする人は、悪い習慣を断ち切るために「飲まないようにする」や「無視する」というような決め事をしている人が大半です。
要するに、悪い習慣を止めようとする人の思考に、それぞれ3つは当てはまっていて。
この3つの中で、「どれが悪い習慣をやめるのに、適しているか」というのを研究したのが、ユトレヒト大学の研究だということですね。
結果として、一番効果が薄かったのは「否定的イフゼンルール」で、例えるなら「お酒を飲みたくなっても飲まない」というルールを作った人が一番悪い習慣を断ち切ることができませんでした。
むしろ悪い習慣だとわかっていても、行動してしまう人も見られ、逆効果であることも確認されました。
一方で、一番効果が高かったのは「代替えイフゼンルール」を使用したグループでした。
このことから、悪い習慣を根絶するためには、「やらないこと」を決めるより、「やりたくなった時に、どんな代替え行動をとるか?」ということを決めることが重要だということが判明したということだったわけです。
やらないと決めることが悪影響な理由

ではなぜ、「悪い習慣はやらない」と決めることが、悪い習慣を根絶させることに効果を発揮しなかったのか。
その理由に関して、心理学の研究の中で有名な「シロクマ実験」というので説明することができます。
このシロクマ実験というのは「シロクマのことを考えないでください」と被験者に伝えることで、被験者は「シロクマのことしか考えられなくなる」というもので。
「〇〇しないでください」とすればするほど、人はそれが気になってしまう、という心理学の研究です。
僕らも日常生活で「この先は覗かないでください」という看板があれば、「この先は何があるんだろう?」と気になってしまいます。
それと同じで「〇〇しない」というのは、裏を返すと「〇〇したくなる衝動」を自らで生み出してしまっているわけです。
先ほどの研究も同様で、「お酒が飲みたくなっても飲まない」と決めたところで、「飲まない」ということが、より「お酒」のことを連想させ、その結果どんどんと読みたい気持ちが強まっていってしまう。
そのことから、逆効果を生み出し、どんどんとアルコールの摂取量が高まってしまう恐れがあるため、否定的イフゼンルールが効果を示さなかったわけでした。
応用方法

つまり、僕らが悪い習慣をやめたり根絶したりするためには、「〇〇をしない」ということを決めるのではなく、「〇〇をする」ということを決める、代替えイフゼンルールが重要だということです。
もし仮に、お酒が飲みたくなったら、「水を飲む」だったり。
「ノンアルコールビールを飲む」だったり。
こういったお酒に変わる代替えを作り、ルール化することが悪い習慣を断ち切るために重要になってくるわけです。
そして。
こう聞くと「お酒を飲みたくなったら、筋トレをする」というように、代替え案を「難しいもの」に変えてしまう人が出てきます。
ダイエットのケースでも「お菓子を食べたくなったら、家の周りを走る」というような例も同様で。
このように代替え案を「難しいもの」にすると、その代替え案(先ほどの例だと「走る」「筋トレをする」が該当)をするのが面倒になり、より楽な「お酒やお菓子」を選択してしまうことが考えられます。
だから、代替え案は「難しいもの」ではなく、「簡単なもの」であることが重要だということは悪い習慣を根絶する上で知っておきたいことです。
「代替え=手軽なこと」
これはぜひ覚えておきたいことですね。
この代替え案を考える際には「悪い習慣を断ち切るためのシンプルかつ強力な方法。」
この記事にあるトリガーに注目するとカンタンに見つかるのでぜひ参考までにどうぞ。
実際にやってみた結果

んで。
僕自身このユトレヒト大学の研究なんかを見て、代替えイフゼンルールを試してみたんですね。
先に結論から言ってしまうと、めちゃくちゃ効果のある心理テクニックだと思います。
上記でも少し触れましたが、このイフゼンルールは習慣化のテクニックの中で、最も強力なテクニックの1つとして紹介されていますが、僕自身やってみて間違いないなって感じていますね。
今でもなにかしら新しく習慣化したいときには、このイフゼンルールを組み込んでやっていたりします。
朝から運動の習慣化作り
まず、実体験から抜粋して、新しく習慣化として作り上げたもの中で「運動」というものがあります。
運動自体、僕は結構やっていたんですがポイントは「朝」から運動するということで、朝から運動することの効果は、様々な研究で知られています。

その朝活に関しては上記でめちゃくちゃ詳しく解説しているので、参照してください。
この「朝から運動する」ということですが、僕はめちゃくちゃ朝が苦手で。
なるべく起きたら1時間ぐらいだらだら過ごしたい人だったんですよね。
それをイフゼンルールを使って習慣化していきました。
具体的には、朝起きたらスマホをチェックしながら煙草を吸うんですが、「1本吸い終わったら、服を着て外に出る」ということをイフゼンルールとしてやっていました。
この「1本吸い終わったら、服を着て外に出る」がイフゼンルールとして機能していたので、何度も繰り返していくうちに、ルーティン化していき、今ではもう当たり前のように朝からの運動が習慣化となっていきました。
代替えイフゼンルール
そして、朝から運動するということが習慣化した後に、今回のユトレヒト大学の発展形として代替えイフゼンルールを応用していきました。
具体的には、この朝から運動として「散歩」をやっていたんですが、散歩からさらに強度を上げた運動をしたいって考えていたんですよね。

それは上記記事で詳しく解説していますが、メイヨークリニックの研究を見たことが由来でした。
ここから「朝から散歩をする」という自分ルールを代替えし「朝から激しいHIITをする」ということにシフトしていきました。
これがめちゃくちゃ功を奏していて。
実は散歩という軽い運動を始める前に、「朝から激しい運動をする」ということをやっていたことがあるんですね。
これが見事に挫折していて。
3日と持ちませんでした。
ただ、すでに「朝から散歩をする」という習慣が根付いた後に、「散歩を別の運動に変える」という代替えイフゼンルールはめちゃくちゃ機能して、スムーズに運動の種類をシフトすることができました。
考えてみれば当然ですが、やるべきことはそこまで変わらず「強度」という内容が変わるだけです。
なので、土台として完成されている習慣に、少しメスを入れるだけなので、スムーズにシフトすることができたなって感じています。
代替えイフゼンルールは最強
こう振り返ってみると、僕自身はめちゃくちゃ効果を感じている習慣作りのテクニックだと思っています。
筋トレや運動の習慣を取り上げたのは、習慣化の中で「かなり難しい部類」といわれているからで、実際に習慣化の研究として題材になるケースが多いのが、運動やジム通いだからです。
僕自身はまず「散歩」という軽い習慣から定着させ、慣れてきたら徐々に強度を上げる代替えイフゼンルールを使ってきましたが、振り返って思うのはやはり「イフゼンルールは習慣化のテクニックとしては最強」だという風に感じています。
それほど難しいことはないし、気軽にできる。
でも、効果はすごい。
実際にやる前までは「こんなことで習慣化なんてできるのか?」って疑っていましたが、慣れというのは恐ろしいもので、「これやったんだから、あれしなくちゃ」という風に徐々に脳にインプットされていきます。
これを心理学用語でトリガーと言ったりするわけですが、代替えイフゼンルールはそのトリガーを利用して「別の習慣を入れ込む」というもので。
ステップ化していくことで、どんな大変な習慣も徐々に定着させていくことができる。
かなりおすすめできる習慣化のテクニックだと実体験からも思いますね。
まとめ
最後にまとめておくと。
悪い習慣はやめようと思っても意味がない。
やめるのではなく、代替えを考えイフゼンルールに落とし込むことが重要。
その際に、難しいことを代替え案として採用しては意味がなく、手軽にできることをルール化しなければいけない。
悪い習慣を根絶する方法をまとめるとこんな感じですね。
ぜひ参考にどうぞ。